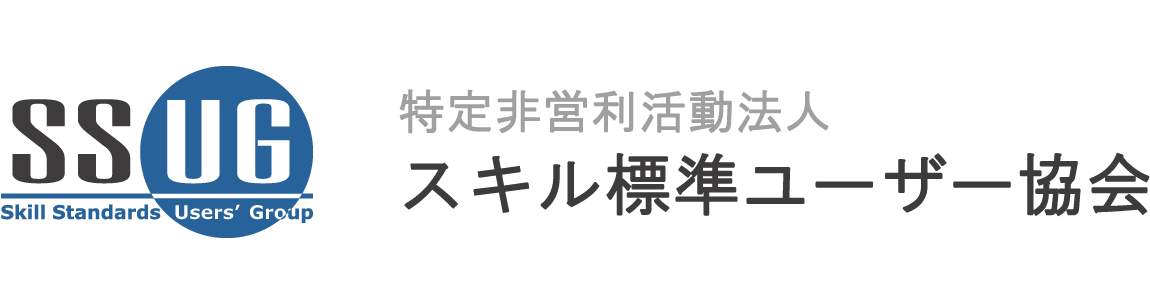●『異業種交流会の勧め』
日立建機株式会社 人財本部
人財開発統括部 主席主管 石川拓夫
10年以上前から有志で人事・人財開発の異業種交流会を立ち上げて、年に3~4回開催している。
コロナ禍でオンライン開催になり、一時低調になったが、今年度からリアル開催としてリニューアルした。
事務やファシリテーションはある教育ベンダーにお願いしているが、幹事は参加企業の持ち回りで、毎回異なる企業を訪問できるのも楽しみである。
この会の基本ルールはひとつだけ。それは参加企業がWinWinの関係を維持することだ。ギブアンドテイクの関係と言ってもよい。情報収集するだけの目的では、情報提供する企業にメリットはないし、サスティナブルではない。参加企業は対等な関係で情報共有し、議論を行い、それぞれの参加企業の明日の施策に反映する。そんな関係性を維持することが大切だと考えている。また参加する人事・人財開発の担当者の方々にとっては、一種の学びのコミュニティである。人事異動などにより、人事・人財開発の経験が少ない方もいる。このような人も含めて参加者にとっては、各社のいろいろな考え方や施策の話を聞くことは、専門領域の学びにつながる。ただの情報交換の場ではない。
この会では、毎回3社が自社の取り組みや課題を発表し、参加者からアドバイスをもらう形式としている。
社外の人に施策のレビューをしてもらうやり方だ。参加者は発表を聞いた後、グループワークで考えを共有し、それを発表という形でアドバイスする。参加企業は産業分野やビジネスモデルが異なるので、様々なアドバイスがもらえる。
同一な組織文化の中では難しい多様な考えがもらえる。これは大変参考になる。
またこの形式だと、発言の機会は全員にあり、全員参加型のワークショップである。まさに学びの場といえる。
こんな会の幹事を2月末に当社が務めた。土浦にある工場で開催し、工場見学も併せて行った。
参加企業は約15社約30名、発表は3社。当社も「学びのコミュニティ」についてこれから本格的に開始する施策の考え方や内容を説明し、参加者からアドバイスを求めた。
社外活動があまり活発ではない文化で、当社の担当者も社外の人と交流すること自体、経験が薄い中で、立派に発表してくれた。アドバイスも予想以上に多く頂けた。当社の担当者にとっても大変良い経験になったことと思う。
工場での交流会の終了後は、場所を移して懇親会を実施。この会のもう一つの楽しみは懇親会で、さらに深い話が聞けることである。社外の交流ということを忘れるほどフランクで高揚感があり、その後個別の意見交換ができる関係構築も可能である。
世はイノベーションの時代になり、オープンな場において、多様な人との交流や協業の中から新しいものを生み出す時代になってきている。そんな中でそれを支える人事・人財開発部門の担当者が、企業の中の価値観だけで施策が立案できるだろうか?
それ以前に、そもそも人的資本経営の時代になって、人事・人財開発部門は戦略部門にならなくてはいけない時代に内向き志向で運用だけ行っているのではないだろうか?またクロスインダストリーの時代になって、他業種だから参考にならないといえるだろうか?
人事・人財開発の担当者が向き合うのは、どんな産業分野であれ、社会情勢に敏感に影響を受けている人々である。
自社の今までの組織文化や風習などに疑問を持たないで役割を全うできるはずはない。
日本の企業や働く人々が少しでも幸せになるために、業界を超えた学びの場は大切だと思う。
それはまた人事・人財開発の担当者のキャリア形成にもつながり、日本全体の人事・人財開発のレベルアップにもつながると思う。決して大げさではない話だと思う。
この会で知り合ったある企業の責任者の方は、最近ほかの職種から異動してきて、人事・人財開発の分野は全くの素人で、なにから手を付けてよいかわからないと相談を受けた。僭越ながら人事・人財開発のラーニングパスを教えてあげた。その方は真剣に紹介した研修などを受講している。これはひとつのエピソードだが、これが多くの企業で行われている人事ならば、これに対応したソリューションはあまりに少ない。このような異業種交流会が、そのソリューションのひとつになると思う。
外に開かれた窓を持つことは、とてもよいことだ。自分一人ではなく、同じテーマで悩み、一緒に考えてくれる同志がいることが、社会人としてとても大きな支えになる。これは人生100年時代には必要な窓でもあると思う。人事・人財開発の担当者の方には、ぜひこのような異業種交流会をお勧めします。
以上